錆びたナイフ
2019年5月30日
[本]
「存在と時間 Ⅲ」 ハイデガー
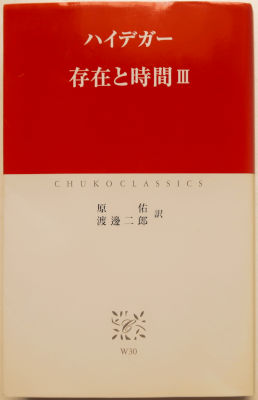
「時間」の話である.
ハイデガーは「過去・現在・未来」のように連続する時間といった解釈を「非本来的な時間了解から生じたもの」として一蹴する.
フランスの哲学者アンリ・ベルクソンの時間解釈は、私の理解によれば、筋肉の動きが経験として「時間」を生み出すという、シンプルで明快なものだった.
ハイデガーは、それでは不十分だと言う.
「時間性は、・・先駆的決意性という現象に即して経験されるのである」
「根源的で本来的な時間性の第一次的現象は到来なのである」
「先駆的決意性」?「到来」?
例えば人が歯を磨こうとするとき、洗面所へ行って歯ブラシを使うという一連の動作は、あれこれの筋肉の動きを経て実現するが、ハイデガーはその時、何故そうするのか、と考えたのである.
それは、自分が歯磨きをする未来に向かって、その瞬間に必要な行為を、時々刻々と選択し判断する意思の上で成り立っている.
歯を磨くという可能性に向かって自らを投げ出すこと、さらに歯を磨いているという未来の可能性を「到来」として受け取ること、そして歯ブラシはここにあるはずという過去の経験を奪取すること、さらにある瞬間に歯ブラシという道具と「出会う」こと、これらの一連の契機の中で「時間」が生まれる.
「企投」「被投」「到来」「既在」「瞬視」といった細かな働きが、次々に変化しながら起こる.
右手で戸棚を開け、左手で歯ブラシを取り出し、それを右手に持ちかえるといった些細な動作の中にも、それらが起こる.
筋肉が動くのは単に結果であって、意識/無意識に関わらず、これら動的な可能性の中で時間が生まれ落ちる=「時熟」する、とハイデガーは言う.
彼が考える「時間」は、一方向に流れるのではなく、「躍動」している.
ベルクソンはいわば空間を時間に結びつけたのだが、ハイデガーはさらに空間について、
「現存在がおのれに空間を許容するはたらきは、方向の切り開きと遠ざかりの奪取とによって構成される」
赤ん坊は、オモチャに向かってハイハイすることで「空間」を作る、のである.
だから、科学がいう客観的な四次元時空はここにはない.
「時計使用の実存論的・時間的意味は、移動する指針を現成化することだと立証される。指針の位置を現成化しつつ追跡することは数えることなのである」
現成化(げんじょうか)というのは、未来と過去と現在を動的に結びつけて現れる「存在・了解」のことである.
時間も空間も「モノ」ではなく、人間が周りを気づかうことに基づく「性質」なのだ.
「実存」というのが人間の可能性のことであり、「到来」という「時間性」のきっかけがその可能性からやってくるのなら、その極北に厳然としてあるのが「死」である.
「この先駆的決意性において現存在は、おのれの存在しうることに関しておのれを了解するのだが、それは、現存在は死の面前へと進み出て、こうして、おのれ自身がそれである存在者を、おのれの被投性において全体的に引き受けるというように、おのれを了解するのである」
「死に向かって先駆する」ことが、最重要課題なのである.
ハイデガーの発想はここへ収斂する.
しかし「死」とは何か.
ハイデガーは死後の世界について言及していないが、若い頃に神学を学んだ彼は、キリスト教の「復活」を信じなかったのだろうか、
「現事実的実存は、生誕を含みつつ実存して、また生誕を含みつつ死へとかかわる存在という意味において、いちはやく死亡してゆきつつある」
私の頭にとっさに浮かんだ「Living Dead」は、「生きている死体」つまり「ゾンビ」である.
1970年代の映画に現れた「そいつら」について、私は「復活」や「即身成仏」の暗黒面と思っていたが、現代社会ではもっと根深い何ものかである.
現代人は、ハイデガーの言うように死を恐れ忌避しているわけではない、思い通りに死ねないことを怖れているのだ.
脳死状態にある人間は、「現存在」でありえるのか.
この第3巻でもハイデガーは、あらゆる概念を実存的に再定義しようとしている.
「自我」「希望」「無関心」「好奇心」「熟慮」「運命」・・なぜか「愛」とか「友情」「家族」といった言葉はない.
「恐れは、世界内部的なもののほうから襲いかかってくるのである。不安は、死へとかかわる被投的な存在としての世界内存在のうちから高まってくる」
「不安」は良いが「恐れ」は良くない、といっているのが面白い.
「不安は、現存在をその最も固有な被投存在に当面させて、日常的に親しんでいる世界内存在の不気味さを露呈させる」
映画「マトリックス」で、誰もが信じる日常世界が実はコンピューターの作った幻想世界で、「リアルワールド」はその底にあって機械虫が這い回る不気味な世界だ、というのを思い出す.
現代人はもうとっくに、ケイタイを使って「マトリックス」に首までつかっている.
それでも「不安」で「不気味」な世界の方へ覚醒せよと、モーフィアスはいうのだ.
「適所をえさせることをわれわれは、実存論的に、「存在」させることだと了解する。この存在させることにもとづいて道具的存在者は、道具的存在者がそれであるところの、まさにその存在者として、配視にとって出会われうるのである」
これも面白い.
故障した道具、あるいは使い方のわからない道具、さらには今必要なのにここにはない道具、という存在は、つまり不可能性という存在として姿を現わすのである.
「道具的存在者」が道具であることをやめたとき、たとえば「電源を入れても黒い画面しか出ないパソコン」、「歳を経て思うにまかせないこの身体」・・
それらは「事物的存在者」ですらない、それは「メタ非実存」とでも呼ぶべきもの、つまり「Living Dead」である.
適所性の彼岸から、ゾンビはやって来る.
この世に「適していない」という「不快」.
それでもなお「この世界にある」ことへの「怒り」.
「存在」への「憎悪」.
ハイデガーが「道具的存在物」ではなく「道具的存在"者"」と呼んだのは、それが「実存」つまり「可能性」そのものだからだ.
すると、「人間が名前をつけたモノ」はすべて「道具的存在者」だということができる.
一方、ハイデガーが「事物的存在者」と呼んでいるのは、それは名付ける前のモノ、すなわち「可能性を剥奪した・道具的存在者」ということではないのか.
それはたとえば「鉄の塊としてのハンマー」であり、科学が対象にしているのは、これである.
科学者のほとんどは「実存」と「実在」を混同している.
この「実存」以前のもの、いわば「メタ存在」と呼ぶものが何であるかは、まだハイデガーの彼方にある.
科学の上では、質量すなわち存在と、エネルギーすなわち可能性とは、等価である.
量子力学は、素粒子のありようを「エネルギー場の擾乱」と考える.
「実在」も「永遠」もこの世にはない、そのことを、昔の人は「色即是空、空即是色」とよんだ.
この書は、確かにわかりにくいが、読めば読むほど、妙にひっかかる.
ジグソーパズルのように、それぞれのピースが、ひらめくのである.
一方で、本来性/非本来性、頽落、世人、といった概念はどうにも収まりが悪い.
ハイデガーは、現存在の本来性と非本来性とは、実存の二つの根本可能性であると言うが、結局、人間は本来性として生きるべきだと考えている.
「非本来性」というのは死に向き合おうとせず、周囲の物事に流され、その日暮らしをするという、まさに我々の生き方なのだが、
「死への先駆のみが、あらゆる偶然的で「暫定的」な可能性を追い払うのである。死に向かって自由であることのみが、現存在に端的な目標を与え、実存をその有限性のなかへと突き入れる。実存のこのつかみとられた有限性は、愉楽や軽率や回避などという、最も身近に押しよせてくる諸可能性の限りない多様性から現存在を引きもどして、現存在をその運命の単純さのなかへと連れこむ」
著者の意気込みはわかるが、いったいどう生きろというのだろうか.
ハイデガーは第2巻の「死へとかかわる存在と現存在の日常性」という節で、
「L・N・トルストイは、『イワン・イリッチの死』という彼の物語のなかで、この「ひとは死亡するものだ」ということがひきおこす動揺と崩壊の現象を、描写してみせた」
という脚注を記している.
『イワン・イリッチの死』は死にゆく男の苦悩を描いた小説で、ハイデガー流に見れば、非本来的な生き方の典型なのだろう.
だが、ハイデガーのこの短いコメントは、この小説を評するにはあまりにずさんである.
「死」に対する洞察力は、どうみてもトルストイの方が数段優れている.
世人が死を遠ざけ日々の気散じに頽落して生きようがどうしようが、最後は誰もが、死に直面せざるを得ない.
それが「臨終」である.
つまり人間には、非本来性の中に本来性が突出する瞬間が必ずある、それを「良心」と呼ぶのだ、と私はおもう.
ハイデガーを読んでいると、「存在」というものが、ドーナツの穴のようなものだという気がする.
世界は、不気味な「穴ボコ」だらけなのだ.
これほどスリリングな世界認識は、ほかにない.