錆びたナイフ
2018年12月21日
[本]
「うたげと孤心」 大岡信
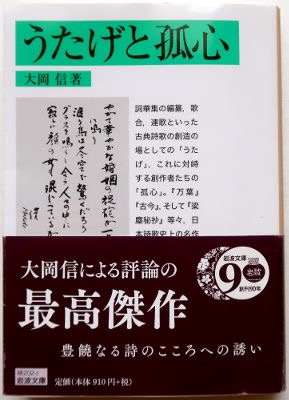
『たえずゆくあすかの川のよどみなば心あるとや人のおもはむ』
『よど川のよどむと人は見るらめど流れてふかき心あるものを』
『そこひなき淵やはさわぐ山川のあさき瀬にこそあだ波はたて』
「古今和歌集」の上記2番目の歌について著者は、
「前の歌を受けて次の歌へとつないでゆくための、いわば遺句めいたところが感じられる。すぐれた歌というものが持っている体臭が感じられず、「よどむ」「流る」「深し」といった語を適当に塩梅して、そつなく一首にまとめあげただけのものである。こういう歌にぶつかると、「よみ人知らず」という文字が何かしらうさんくさいものに見えてくるということになる」と言う.
平安初期の私撰集「古今和歌六帖」の歌と比較しながら、著者は、この歌が「よみ人知らず」ではなく、古今集の編集の都合上、紀貫之が創作したものではないかと推理している.
「勅撰漢詩集、勅撰和歌集のような、祝賀という動機を根本にもっている詞華集の編纂」であるからこそ、こんな(勝手な)ことがあり得る、と見ている.
「笑いの共有、心の感合。二人以上の人々が団欒して生みだすものが「うたげ」である」
しかし一方で、歌を作る行為は純粋に個人の内面の創作活動であり、これを著者は「孤心」と呼んでいる.
和歌だけでなく、連歌、俳諧の連句も、今から見れば、はるかに知的なゲームや言葉遊びに近かった.
「日本文学の中に認められる独特な詩歌制作のあり方」はこの「うたげと孤心」で成立していると、詩人である大岡信は言う.
「公子と浮かれ女」の章は、藤原公任(きんとう)と和泉式部を論じている.
これがすこぶる面白い.
「思いかえせば、あの「くらきよりくらき道にぞ入りぬべき」という歌は、和泉という女の生きかたをもののみごとに予言していた歌だったのかもしれぬ。あの女には、あれ以外の歌い方は何ひとつありえないのではなかったろうか。
公任はここまで考えてきて、ふいにぞっとした。こんな風に歌うほか、どんな歌い方も知らない歌人が、現実に、身近に存在しているということを、今までただの一度も真面目に考えたことがなかったことに気づいたからである。自分は歌についてなら何でも心得ている、と彼は思っていた。けれども、和泉のあの暗く輝く夜の火山の頂きのような歌は、ほんとうは、自分の知っている歌の世界と、ほとんどまったく縁のない世界で、噴きつづけ、燃えつづけている恐ろしい炎なのではなかろうか。
公任は自分が和泉に恋をしかけるのをためらった理由が、深くこの問題とかかわっていたらしいことに、今さらのように気づいて、思わず顔を撫でた」
平安時代に、帥宮(そちのみや)と公任と式部とで交わされた贈答歌、それぞれたった31文字の「ことば」から、これだけの心情を想像するすごさよ.
言語は、単に対象を言い表すだけではない、同時に言語を発する話者自身の立場と思いも表現する.
「思わず顔を撫でた」のは、公任だけではなく、何か思いあたったのだろう、大岡自身でもある.
『ゆく春のとめまほしきに白河の関を越えぬる身ともなるかな』
「行く春を関の手前でひきとめたいと思ったのに、白河の関を越えてしまう身となってしまった」
いやちがうのだ.
公任と式部にとってこれらの歌は、プライベートな思いとほのめかしの洪水なのである.
公任の白河別邸に咲く梅の話が元で、歌のやりとりが始まったのだが、「白河の関」とは、公任の恋愛心のガードの固さのことであり、式部の夫・橘道貞が陸奥守として赴任するために超えた白河の関所のことでもある.
これらは、かなりヤバイ恋愛の歌なのである.
著者の想像力は、千年前の男女の秘めたるスキャンダルを読み解いて、まるでミステリーを読むようだ.
後半の「帝王と遊君」「今様狂いと古典主義」「狂言綺語と信仰」は後白河法皇と今様論である.
後白河法皇は中世日本の巨魁であり、今様は、いわば当時のフォークソングである.
「その歌が永続的な魅力をもちうるかどうかの鍵のひとつは、言葉のひとつひとつとどれほど真面目に付合うかという点にかかっているだろう。当今のフォークソングでは、言葉のひとつひとつがあまりにも無意味無造作無趣味に採用されているために、人の注意を長くひきとめておくことのできないものが多い」
これは可笑しい、大岡はいまどきのフォークソングが嫌いらしい.
「この今様狂いの帝王が到達した思想は、要をとっていえば、一心に心を澄まして謡え、自らは何ひとつ神仏に求めるな、ひたすら心を澄ましておのれの信心の行為である歌にうちこめ、さすれば、神も仏も感応するであろう。その感応は、当然ながら、自夯自身にではなく、他人の耳目にあらわれるであろう、という具合に要約できるだろう」
大岡は、宗教行事としてあるいは「うたげ」としての今様の中に、法皇の「孤心」を見ている.
白楽天の、
『願はくは今生世俗の文字の業、 狂言綺語の誤りをもって 翻して当来世々讃仏乗の因転法輪の縁とせむ』
から、
「狂言綺語の誤ちが仏を讚歎する機縁となる、という思想が、白楽天の詩句から全く逸脱してしまっているかといえば、そうともいえない。にもかかわらず、やはり質の変化が生じたことは否定できまい。簡単に言えば、否定的要素が欠け落ちてしまって単純な肯定という面が露わになったのである」
この「転倒と見切りの力学」は、今様を極めそれを習得するということ、あるいは思想のダイナミズムと等価であり、大岡の視点は単なる歌謡論を超えている.
巻末の解説で、三浦雅士が大岡の「仏法のさとり」を引用している.
「ここでの肝心な言葉は、「ひとり仏にさとらるるゆゑに」というところにある。仏をさとるのではなくて、さとった瞬間、人は仏にさとられているのだ」
また『正法眼蔵』から、
「言葉がものを表現するのでなく、ものが言葉をして自己表現させるとしか言い様のない、絶対的な表現の世界がここにはある」
言語認識は、ついにここまで来るのだ.
冒頭の3首の歌について著者は「すぐれた歌というものが持っている体臭」という言い方をしているが、その根拠は何かとさらに問えば、著者の経験としか言いようがないだろう.
「過去一千年間に日本のすぐれた詩人たちが駆使してきた大和言葉は、いわゆる「てにをは」の絶妙な行使によって、詩歌の最も精彩ある、繊細をきわめた部分を生みだしたと言っていい」
大岡は「絶妙な行使」とは何か、とは言わない.
まるでソムリエがいいと言うからいいワインだ、とでもいうように、全身で「歌」にぶつかり、古典文芸批判を思想のレベルまで押し上げた.
戦中戦後を生きて、大岡信は昨年亡くなった.