錆びたナイフ
2018年10月24日
[本]
「神聖喜劇 全五巻」 大西巨人
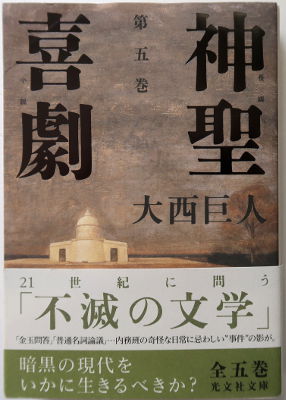
1942年、太平洋戦争勃発後、三ヶ月教育召集兵として、対馬の陸軍野砲部隊に配属された東堂太郎二等兵が主人公である.
軍隊内の陰湿ないじめと、支配地住民への暴虐ぶりと、貧弱な装備をもって特攻を美化した異様な精神と、我々の旧日本軍へのイメージはひどいもので、
その日本軍に、インテリの主人公が初年兵として配属される物語など、うっとおしくて読む気になれない.
ところが、これが、実に面白いのである.
単なる戦争小説でも反戦小説でもない.
これは軍隊を舞台にしたエンターテイメント小説である.
まずその、すさまじい引用文の嵐に圧倒される.
古今東西の文芸文学から哲学社会学歴史学の論文にいたるまで、主人公の頭の中に沸き上がる記憶の断片は際限がなく、次々と話が飛ぶ.
物語の中心は軍隊生活の三ヶ月間なのだが、話は時間順ではなく、入隊前の新聞記者であった頃から、学生時代に官憲に尋問されたこと、愛人との「房事」、果ては少年時代の初恋の思い出まで、縦横無尽.
英語/ドイツ語/漢文/和歌/俳句/詩/民謡から猥歌、さらに状況に変じて戯曲まがいの台詞まで入り乱れる.
二等兵の月給は5円50銭で、諸費用を差し引けば、休日に街の売春宿へ行ける者などいないという、これほど詳細に軍隊生活を描いた小説を、私は他に知らない.
日本軍へのイメージが変わる.
「私は、この戦争に死すべきである。戦場は、「滑稽で悲惨な」私の生に終止符を打つであろう」
「世界は真剣に生きるに値しない、本来一切は無意味であり空虚であり壊滅するべきであり、人は何を為してもよく何を為さなくてもよい」
こういう虚無主義の主人公が軍隊で発見したのは、
「特種の法治主義的・制定法主義的領域と私が考える軍隊兵営で、軍人は、殊に営内居住の下士官は、おびただしい法令(規定) の支配下に生活している。彼らの日常的起居寝食は『軍隊内務書』、『内務規定』、『陸軍礼式令』などによって代表的に制約せられる」
九州帝大の法科中退、アスペルガー症候群かとも思わせる驚異的な記憶力を持つ主人公は、これらの規範を盾に、
「彼らが、彼らの無知無学不見識の結果を・・・私にーわれわれ新兵にーどこどこまでも是が非でも押しつけようとするのならば、私の持ち合わせる学問、知識、教養、見識、猪口才、小癪、こざかしさ、生兵法でもなんでもかでもを総動員して、彼らと競り合い、彼らに干渉し、彼らの穴を探し揚げ足を取ることを、辞せないがよかろう。それが虚無主義者に似合いであろうと不似合いであろうと構うものか」
と決意する.
上官にとって、これほど扱いにくい部下はあるまい.
日本軍は愚劣なこじつけとパワハラがまかり通る理不尽な組織というだけでなく、すこぶる筋が通った一面もあった.
近代軍隊は、高度な兵器とともに、必然的に、合理的な行動をとる兵士を必要としたのである.
軍隊内部の規範は兵士の一挙手一投足に到るまで詳細なマニュアルを定めたが、それは兵士が一個の戦闘マシンとして機能することを目指している.
しかるに問題は、徴集兵のほとんどは農民漁民炭鉱夫らであり、軍が望む戦闘マシンたり得ないのである.
数の数え方から敬礼の仕方まで軍隊式があり、兵士はそれをたたきこまれる.
家族への便りに、食事のおかずが大根ばかりだと書けば、それが軍事機密だと難癖をつけられ、
「知りません」と言ってはならない「忘れました」と言えと強要される.
軍隊の合理性がひん曲がって、どうにも滑稽な人間模様が現れる.
ここで、いったい何が起こっているのか.
東堂は「大和魂」だの「武士道」などの精神論を、決して口にしなかった.
この男は、軍隊を嫌悪しながら、それを構成する人間たちの挙動が面白くてしょうがなかった、あるいはそう思うほかなかったのだろう.
破損した何者かの銃剣の鞘(さや)が、別の兵士のものと入れ替えられ、同僚の冬木二等兵が容疑者にされるという事件が起こる.
冬木が部落の出身者であることと、彼の過去の犯罪が謎の伏線になっている.
隊内で何事かが起こっているという不審不安の描写は見事で、まるでミステリーを読むようである.
東堂はあたかもシャーロックホームズのように、この事件の真相を明らかにしていく.
東堂が私物として持ち込んだ書物は、『広辞林』、『コンサイス英和辞典』、『縮刷緑雨全集』一冊本、『三人の追憶』、『民約論』、『暴力論』、"Buch der Lieder", "A Farewell to Arms"および『田能村竹田全集』
どれも常人が余暇に読むような本ではない.
しからば、田能村竹田という江戸時代の文人画家の講釈が延々と出てくる.
隊内の友人から借りた『筑紫神社志』という神社資料の解説も延々とある.
部落民に関する言葉のいわれは、延々16ページも続く.
隊内で起こる大小の事件が佳境にはいると、作者あるいは主人公の記憶の虫がうずくのか、事件そっちのけで話が飛ぶのである.
読者はあきれて、もはや脱帽と言うしかない.
作者のこういう偏執ぶりが徹底すればするほど、作品は喜劇じみてくる、とも言える.
この小説で最も印象的な人物は、東堂ではなく、大前田軍曹だ.
この男、骨の髄まで日本軍人の傲岸さと執念深さを身につけていながら、その眼力は時代を透徹している.
日本帝国思想の正義漢として登場する村上少尉は、この戦争がアジアの解放につながると力説するが、大前田軍曹の前では影が薄い.
あたかも「罪と罰」のスヴィドリガイロフ、あるいは「白痴」のロゴージンのごとく、彼は単なる悪をこえた存在である.
大陸の戦闘で中国人を焼き殺したと豪語する大前田は、戦争の狂気の体現者であると同時にこの戦争を引き起こしたものへの指弾を平然と口にする.
それが強烈な憎悪のような形で、東堂の反戦感情にぶつかる.
戦争を発案し指揮したのは、愚昧な軍人や政治家たちではない.
高度な教育を受けたインテリゲンチャ官僚たちである.
知識そのものが、モンスターと化すのである.
私は、この大前田軍曹が最後に引き起こした情痴事件の顛末には釈然としなかったが、戦争小説は、この男を主人公にして書かれるべきだと思う.
この小説には登場しない戦場も、はたして「神聖」な「喜劇」たりえるのか.
「天皇は、絶対無責任である。軍事の一切は、この絶対無責任者、何者にも責任を負うことがなく何者からも責任を追求せられることがない一人物に発する」
東堂二等兵が見抜いた日本軍の本質である.
これは、時代を超えた日本社会の本質でもある.
しかし、責任とは、いったい何か.
日本から天皇制が消えるとき、一切の人種・階級・男女差別も消滅するだろう.
差別がなければ、敵味方の差別もない、戦争もない.
しかし、世界とは「差異」そのものである.
差別のない社会とは、いったい何のことか.