錆びたナイフ
2017年5月8日
[映画と本]
「めぐりあう時間たち」 2002 スティーヴン・ダルドリー

「ダロウェイ夫人」 ヴァージニア・ウルフ
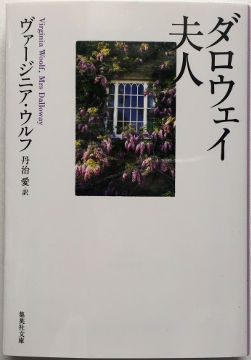
映画「めぐりあう時間たち」の原作者はマイケル・カニンガムで、ヴァージニア・ウルフの小説「ダロウェイ夫人」に触発されて書かれた三人の女性の逸話である.
1920年代ロンドン郊外で暮らすヴァージニア・ウルフ(ニコール・キッドマン)と、1950年代アメリカ中流家庭の主婦ローラ(ジュリアン・ムーア)と、現代(2001年)のクラリッサ(メリル・ストリープ)の話を錯綜しながら描いている.
映画のヴァージニアは「ダロウェイ夫人」を執筆中で、自殺願望のローラは「ダロウェイ夫人」を読んでいる.
クラリッサは「ダロウェイ夫人」の主人公と同じ名前で、その日、パーティを開こうとしている.
どこか思いつめた三人の女たちに死の影がちらつく.
陰鬱な雰囲気だが、映像も構成も一級の作品である.
しかしイギリスならともかく、こんなユーツなアメリカ映画は珍しい.
召使いを何人も雇うようなヴァージニアの邸宅と、戦後成長期のアメリカのローラと、現代ニューヨークに暮らすクラリッサ、この三つの時代はまったく違う.
なぜみんなこんなに苦しんでいるのか.
子供を近所にあずけて、一人自殺しようとするローラの話は、地鳴りのような不安に満ちている.
ローラが横たわるホテルの部屋に、水があふれ部屋を呑み込むシーンはまるで「シャイニング」だ.
優しい夫と子どもがいて第二子を妊娠しているローラがなぜ死のうとするのか、実はよくわからない.
ヴァージニアが精神的な病で自殺未遂を繰り返したというように、自殺がその唯一の解放であるかのように、どうにも重苦しい閉塞感だけはひしひしと感じる.
そしてこの、母親に捨てられる子どもが、クラリッサのパーティの主役である詩人リチャードである.
女性と暮らしているクラリッサの娘ジュリアは人工授精で産まれた.
同性愛者であることでこの世を生き抜いた、とでも言うように、クラリッサの生きる「現代」はなんでもありで、異性/同性の愛は妊娠という「くびき」さえ超えている.
しかし、彼女たちの「苦悩」は、何も変わらなかったのか.
「要するに人間性なんだ、ぼくにのしかかってくるのは」青年が言う.
「われわれは健康でなければならぬ。そして健康とは均衡なのだ」青年の医者が言う.
小説の中では、第一次大戦で精神的な傷を負った青年セプティマスが自殺し、映画では、ゲイでエイズを患っているリチャードが、クラリッサの眼前で投身自殺する.
映画の原題は「THE HOURS」
「自分があらゆる場所に存在している感じがするの、と。「ここ、ここ、ここ」にいるだけじゃなく・・あらゆる場所に」
小説「ダロウェイ夫人」は、一人称と三人称と台詞が地の文の中に渾然として、独特のテンポをもっている.
ロンドンの街中を歩く登場人物とその想いが次々と入れ替わる展開は、J.ジョイスを思わせる.
こんなユニークで面白い文章は比類がないが、その話が面白いかといえば、一向に面白くない.
「むろん彼女(ダロウェイ夫人)は人生を大いに楽しんでいる。楽しむのは彼女の本性なのだ」
「どれほどわたしがこういったもののいっさいを愛しているか、世界中の誰にもわからないだろう。どんなに一瞬一瞬を愛しているか・・・」
「どういうわけか自分が彼に似ている気がする、自殺をしたその青年に。彼がそうしたことをうれしく思う。生命を投げ出してしまったことをうれしく思う。時計が打っている。鉛の輪が空中に溶けてゆく。彼のおかげで美を感じることができた。楽しさを感じることができた」
イギリス社会の階級を超えた羨望や憎悪、人間同士の限りない誤解とすれ違いをぜんぶひっくるめて、ウルフはこの世に生きる意味を、あれもこれもと提示してみせる.
映画は、ニコール・キッドマンの、宙を舞うような目つきが印象的で「暗い」のだが、ウルフの小説は饒舌で明るい.
でもそれは見かけだけのことで、第一次大戦がやっと終わった束の間の平和の、この息苦しさは何なのか.
ニューヨークのクラリッサが、小説のダロウェイ夫人に一番い近いだろう.
精一杯生きて人間の愛と信頼を知り抜いているはずの彼女に、解放感がない.
では「解放されたい」のかと問えば、そうではないのだ.
女性の役割を強制する社会の圧力が、ウルフの時代にも、戦後のアメリカ社会にもあったのだろうが、ウルフの心の底を突き動かしているのは、社会への不満ではない.
「わたしはひそかなたくらみによって生命をくすねるように生きてきた」ダロウェイ夫人.
嫉妬も羨望も愛も絶望も、そしてパーティも、生きるための手段なのだ.
あ、それしかない、のだ.
ウルフが「神」を口にしないその分だけ、生きる力「無意識」が枯渇しているのだ.
「バージニア・ウルフなんかこわくない」(1996 マイク・ニコルズ)という映画があった.
エリザベス・テイラーとリチャード・バートンのすさまじい夫婦喧嘩で、忘れられない作品だが、犬も喰わない話を、極限まで追い詰めて、これしかないでしょ、と彼らは言っているのだ.
彼らはかろうじて踏みとどまっているが、そんなにイヤならニンゲンやめたら? という現代の洪水が、足元からせりあがってくる.