錆びたナイフ
2016年7月31日
[本]
「生物の世界」 今西錦司
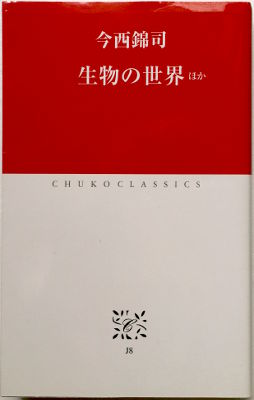
生物学者今西錦司が、戦中の1940年に発表した反ダーウィン説
今西は「生物はすべて環境に対して働きかけ、また環境によって働きかけられることによって生きてきた」のであるから、「結局環境に淘汰されていわゆる優勝劣敗の優者しか残りえないものとするならば、生物のやっていることは創造ではなくて投機である」と、ダーウィンの進化論を批判する.
つまり、遺伝子のランダムな変化を受け継いだ生物が、自然淘汰を生き抜いたらビンゴ!、などというでデタラメでなく、生物自身がもっとちゃんと適応しようとしている、と言うのだ.
今西はカゲロウの幼虫の地域分布を研究して、それらが巧妙に棲みわけをしていることから、生物同士は競争しているのではなく、共存しているのだと言う.
さらに個体だけでなく種にも「主体性」があると考える今西は、生物は種としての共同体や、地球を含めた生物全体を見なければだめだと力説する.
地球ガイア説の萌芽である.
「中生代を通して爬虫類という一つの類縁共同体が生物の世界を支配した。爬虫類が新しい世界を創造して行ったのであって、魚類も昆虫もこの時代の歴史的発展には積極的に参与しておらなかったといえる」
(今西が何故か恐竜と呼ばない)その爬虫類が滅んで「新生代はまさしく哺乳類の時代」となり、
「このようにつぎの支配階級を担うべきものが崩壊するべき支配階級の中から出てくるといったところに、われわれは生物の社会における階級がどこまでも身分社会というにふさわしい性質を帯びたものであることを知るとともに、身分社会なるがゆえに庶民階級としての昆虫類からでは、しょせんなろうにも支配階級にはなりえなかったという解釈もつくのである」
「すると生物の世界の歴史、生物進化史というものも、それは一応支配階級の興亡史であると定義されるかもしれない」
「現在は人間が支配階級で大いに創造的進化を遂げている」
昆虫が庶民階級というのが可笑しい.
今時、人間が生物の支配者であるなどと言ったらそれは、だから人間はロクでもないことをするという否定的な意味だろう.
今西の説は、古い手塚治虫の漫画を見ているような気がする.
戦時日本の高揚した気分が、今西の学説に反映したのだろうか.
私が子供の頃に、これらどこか懐かしいような「階級」という価値観が、まだ残っていた.
今西の文章はセンテンスが長くて読みにくい.
図や表や実証的な論証がほとんどなく、生物、生命、意識、認識といった基本的な知見を無自覚に乱発するので、理論的に不明瞭なこの書は、論文というより「ファンタジー」である.
「植物の社会のような発達段階の低い社会」とか「進化の段階の低い魚類とその段階の高い哺乳類」とか、今西は、進化はすなわち発達、創造、進歩であると考えている.
ダーウィンは、進化論を提唱した当初、進化という言葉を使わなかった.
彼が「種の起源」で提示したのは、種は変化する、ということである.
ダーウィンは、変化を進化と呼ぶことで、それが進歩ととらえられることをおそれたのだ.
人類が猿から進化したことは、人間はサルより進歩したということではない.
何故ならサルもまた、今のこの世界に生きているからである.
「種の起源」が西欧社会を揺るがせたのは、生物が環境で変化するという発想ではなく、生物は神が創造したのではないということ、人間は生物の中で特別な存在ではないという発想である.
彼はそれを自然の中から学んだが、キリスト教が流布した、人間は特別だという発想は、はるかにしぶとかった.
巷にあふれる「進化したクルマ」とか「進化した生活スタイル」とか、「進化」=進歩=より改善されたものとする考えは、ダーウィンとは無縁である.
ダーウィンの自然淘汰とか適者保存という原理は、実は生きているものは生きていると言うのと同じで、単なる結果論であり、それが進化の原因であることを証明する方法はない.
ヘラジカの巨大化した角や、オスの孔雀の羽根など、環境に適応したというより、自然の気まぐれでそうなったと考えるほうが真っ当だと、私は思う.
今西は種の起源について「世代を重ねて行くうちに次第にそのような変異を呈する個体の数が増して行って、いつの間にか種自身が変わってしまうのである」と言っている.
なんとも木で鼻をくくったような説明でがっかりする.
今西は、1984年に発表した「自然学の提唱」の中で、生物進化は「豪華絢爛たる一大絵巻物というか、あるいは壮大きわまる一大ドラマ」であり、「一大ドラマである進化と対面した私は、いさぎよく自然科学と訣別することになった」と言っている.
科学者をやめてしまったのである.なぁんだ.
しかし、よく考えれば、そもそも、進化論は科学ではない、のではないか.
「種の起源」の中に、種の起源は書かれていない.
種が変化することと、新たな種が誕生することは別の話である.
ダーウィンは正直に、そこはまだよく分からないと言っている.
キリンが高い木の葉を食べられるように適応しているのは事実だが、そのためにかつて短かったキリンの首が長く伸びたという証拠はない.
そもそも首の短いキリンはキリンではない.
キリンは、生物史の中に忽然と現れるのである.
ことほどさように、進化論の世界は胡散臭いのである.
今西もダーウィンも、自然から大きな感銘を受けたことに違いはない.
生物同士は生存競争をしているのか、共存しているのか、孔雀の羽根は自然の気まぐれか、生物の主体的な美しさの現れか、所詮人間は、人間の歴史と人間社会のアナロジーでしか世界を見ることができない.
それは人間の世界認識そのものが、人間の存在そのものであるからだ.
生物の進化論は、人間が語るかぎり、その見かけが虹色に変化するファンタジーなのである.