錆びたナイフ
2016年6月17日
[本]
「本居宣長」 小林秀雄
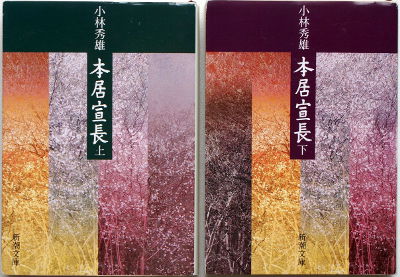
江戸時代の国文学者・本居宣長(1730-1801)の古文研究と、その時代の「学問のありよう」を論じている.
研究の対象は主に「古事記」(712年)と「源氏物語」(1008年)で、江戸時代に古代を再発見しようとする試みが興味深い.
宣長はその著作で、ひたすら古文そのものに没頭し、地道に註釈を加え、古代の人間と神を再現しようとした.
江戸期の学者の引用文は、漢文混じりでひどく読みにくいが、小林秀雄の論旨は明確で、分かりにくい所はない.
小林の論じる学問の範囲は広く、契沖、林羅山、伊藤仁斎、荻生徂徠、賀茂真淵、平田篤胤、中江藤樹、荷田在満、上田秋成といったそうそうたる学者たちが登場、すったもんだの騒動が面白い.
仏教、儒教、朱子学が主流であった江戸期、遥か欧州は、重商主義を背景にした啓蒙思想の時代であり、理性や実験・観察を重視する自然科学が急速に発展した時代でもある.
それに呼応するかのように「知を致さんと思うなら、先ず物の理に至り、これを窮めよ」と考える日本の学者たちに、古事記の神代は絵空事に見えた.
宣長の主張は、まず古文そのものをよく読み丸ごと信じるべきだ、という単純なものだった.
宣長の主張は多くの反発と誤解を生むが、小林は、宣長の著作を丹念に追うことで、その真意を探ろうとする.
「幾百年の間、何とかして漢字で日本語を表現しようとした上代日本人の努力、悪戦苦闘と言っていいような経験を思い描く・・という事が、宣長にとっては、「古事記伝」を書くというその事であった」
遣隋使/遣唐使によって伝えられた圧倒的な中国文明の前で「日本語文字」を編み出す奇想天外な方法は、単に漢字に訓読みを当てはめる、というようなことでは済まなかった.
この中国文明はその後も、漢文というかたちで大きな影響を与え続けるが、あたかもヨーロッパで、ラテン語という知識人言語に代わる自国語の出版物が、ルネサンスを生んだように、
『からぶみにいへるおもむきは、皆かの国(中国)人のこちたきさかしら心もて、いつわりかざりたる事のみ多ければ、真心にあらず』という反発が、この国(日本)に起こる.
「古事記」の創出は、単に各民族が持つ創世神話のひとつではなく、日本人が自らを意識するという最初の営為だったのだ.
「宣長の「源氏」による開眼は、研究というよりむしろ愛読によった」
『人にかたりたりとて、我にも人にも、何の益もなく、心のうちに、こめたりとて、何のあしきこ事あるまじけれ共、これはめづらしと思ひ、是はおそろしと思ひ、かなしと思ひ、おかしと思ひ、うれしと思ふ事は、心に計思ふては、やみがたき物にて、必ず人々にかたり、きかでまほしき物也、その心のうごくが、すなはち、物の哀をしるといふ物なり、されば此物語(源氏物語)、物の哀をしるより外なし』
宣長の言う「物のあはれ」は、幽玄やわびさびでもなく、人生の機微あるいは生きる糧といったような意味だ.
「彼の課題は、「物のあはれとは何か」ではなく、「物のあはれを知るとは何か」であった。彼は、知ると感ずるとが同じであるような、全的な認識が説きたいのである」
小林は、宣長の研究態度を通して、まず古文に心底没入して原作者の世界が手に取るように出現しなければ、いくら理屈を振り回したところで、本当のところは理解できない、と再三主張する.
それは、学問とは何かとか人間とは何かといった、理解すればするほどいわく言いがたくなるものを、小林もまたよく知っていたからだ.
そして言い難いものを蹴散らすような、誤解と無理解が蔓延する学者たちの世界を、小林は遠回しに嫌悪している.
この本(「本居宣長」)を語るということは、例えば紫式部が光源氏に語らせたことを本居宣長が語り、それを小林秀雄が語り、さらに私がここで語る、という重複した構造を持つことになる.
小林は、宣長が「古事記」や「源氏物語」でそうしたように、宣長の著作と手紙を熟読し、その曰く言い難い思いを辿って、学問とは何かという近代のテーマに迫ろうとしている.
そうでなければ、宣長を読んだことにならない、と小林は考えている.
しかし、小林の主張には、その先がない.
時代を越え社会を越えて、ある文芸作品を理解するということは、読む側のある種の「飢え」に依存しているのだと私は思う.
優れた作品が持っている説明し難い魅力とは、同時にあらゆる多様な理解と等価であり、誤解と誤読そのものが、その時代の思想を背負っている.
宣長には、誰が何と言おうが、古文を通して古代の人間の心をつかんだという解放感がある.
しかし、それを指摘する小林自身に、閉塞感を感じるのは何故だろう.
私には、この世(現代)はキライだという、小林の癒されない「飢え」の声が聞こえるような気がする.