錆びたナイフ
2015年7月28日
[本]
「デカルトの骨」 ラッセル・ショート
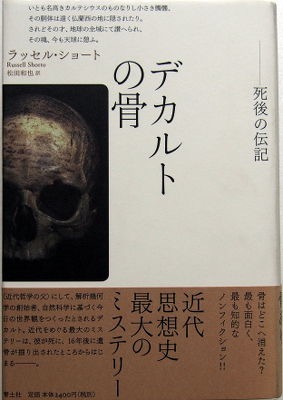
17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトの、その「骨」をめぐる話である.
デカルトはスエーデンで客死し、遺骨はフランスへ帰ったはずだが、なんと頭蓋骨の行方が分からなかった.
どこやら「ダ・ヴィンチ・コード 」を思わせる歴史ミステリーに加え、ジャーナリストである著者は、デカルトの「方法序説」に始まった「近代」とは何かを考察している.
われわれの精神(そして魂)は物質世界とは別個に存在するという「デカルト的二元論」の、その「物質」に過ぎない骨をめぐって、御本人の死後、あたかもキリスト教の聖人の遺骨のように、デカルト主義者に崇められた骨はヨーロッパを彷徨う.
発見された骸骨から顔を再現し、肖像画と照らし合わせて本物だと推理するという「合理性」の勝利の一方で、脳の大きさはその知性に比例するというデカルト主義者の「科学的」な論拠を元に、かの頭蓋骨の大きさを測れば、小さめだった、というのがとても可笑しい.
「前提を疑う、信仰を根拠としない、伝統ではなく立証可能な観察に基づいて世界観を構築する・・・これこそ、民主主義や心理学をはじめとするありとあらゆる近代的なものの発達の出発点となったのだ。」
彼の死後半世紀を経てイギリスにニュートンが登場し、18世紀末にはフランス革命が起こり、19世紀にはダーウィンが登場し、デカルト主義はその歴史の大波の震源であったと著者はみている.
「十九世紀初頭ともなれば、科学に対する信仰も既に揺るがぬものとなり、ごく普通のキリスト教徒ですら、例えば天地創造だのノアの洪水だのの証拠を科学的に証明することができると考えるようになっていた。」
デカルトが神を信じていたように、初期のデカルト主義者の多くはカトリックの司祭であり、ニュートンはプロテスタントだった.
デカルトの「骨」を巡って、著名な科学者たちがきら星の如く登場するこれらの時代は、実は科学とエセ科学と宗教のごった煮時代だったのである.
教会で信徒に配るパンとぶどう酒は、キリストの肉であり血である.
聖書にそう書かれてあるからである.
「教会にとって、キリストは「真に、現実に、実体的に」パンとぶどう酒の中にいたのであり、そうでなければならなかったのだ。」
それは象徴としての意味だとプロテスタントは言い抜けたが、カトリックは科学と葛藤し、科学を呑み込もうと苦悶する.
これはパンであるが実態としてキリストである・・それがすなわち奇跡なのだ・・・
これは当時の「知的で合理的なカトリック教徒」の弁である.
デカルトは、数学者であり天文学者であり解剖学者でもあった.
しかも「デカルトは自己中心的な虚栄心の塊で、決して恨みを忘れない男だった。ゆえに家族とも疎遠であり、親しい友人などもほとんどいなかった・・」
肺炎で死ぬ間際にこの男は、祈祷と瀉血しかないスエーデンの医学を呪った.
人間が病気になるのは、善行を怠ったからでも、悪魔が取り憑いたからでもない、馬車が動かなくなったら人はどうするか、人体も同じように「修理」すればいいのだ.
人間の身体は機械と同じく機能の集合であるというその発想は、その後の世界の医学に決定的な影響を与えた.
かくて21世紀、西欧は辛うじて宗教を乗り越え近代合理主義に到達した、と思われたが、著者は最終章で立ち止まる.
「宗教は芸術と同様、リアリティの複雑さに対処するひとつの方法なのだ。二元論という哲学的難問、そしてそれを解決しようとするあらゆる試みが、リアリティの複雑さを認めている。」
世界は、デカルトが考えたより何倍も複雑で多層的だったが、合理主義の代名詞である「科学」は、その解明に成功したかに見える.
デカルトの末裔である我々の、理性的で合理的な言動は、今や「グローバルビジネス」と名を替えて世界を席巻しつつあるが、予断は許さない.
人類の行為は「非論理的」であり、有史以来、合理的であったためしなどない、とバルカン星人のスポックが言う.